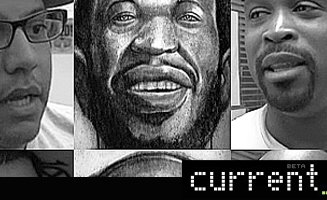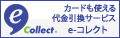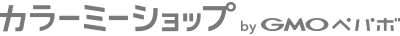year/2010
country/Japan
label/Grunt Style
Wax Poetics Japanの第10号。Fela Kuti、Style Warsの他、Tony Allen、Rich Medina、MUTE BEAT、Don Letts、Guru、Teddy Pendergrass、Saravah Soul、Marcos Valle、Flowering Inferno、12×12: The Breaks、The Five Corners Quintet、The 45 Adapters、12inch Laboratory、ヴァイナル駅伝、Funk Archaeologyなど多数の濃厚な記事を掲載。
-以下卸元より-
Fela Kuti
アフロビートの創始者であり、ナイジェリアの英雄であるフェラ・クティ。アメリカ本国へ渡ったフェラ・クティ本人が受けた衝撃や葛藤を事細かく記載。マルコムXの影響や、どのようにアフリカ回帰をしたのか。85年に出版された有名なフェラ・クティに関しての書籍「This Bitch of a Life」からの抜粋。「1963年にイギリスから帰国したあと、俺はナイジェリアのラジオ局NBCにプロデューサーとして就職した。ひどい仕事だった。でもその傍ら、俺はレコードに没頭し、アフリカの音楽を聴きまくったり、バンドを結成して活動していた」
Style Wars
1973年1月にニューヨークに移住したヘンリー・シャルファントは、もともと彫刻家として活動していた。彼はアップタウンにあるアパートからソーホーのグランド・ストリートにあるダウンタウンのスタジオまで通勤することが日課だった。電車で毎日、グラフィティが進化していく様子を目の当たりにし、次第にグラフィティの世界に夢中になった彼は、初歩的なタグが、ホール・カー、トップ・トゥ・ボトム、キャラクターといった作品へと変貌していく過程を目撃して魅了された。
Tony Allen
ロンドンに到着したトニー・アレンは「こんなところに来た記憶はないね」と言った。アレンが訪れた50年前のロンドンは散々増幅された現在のこの街とは全くの別世界だったろう。悲鳴を上げるこの街のスピードとスケール感。我々がここに来た目的を示すかのように「ビジネスのためだけの街さ」とアレンは語る。アフロビートをかじった程度の人には“フェラ・クティのドラマー” としてのみ知られる彼は、ラゴスのナイトクラブに響いた壮絶な音楽の作家であり大ベテランである。
Rich Medina
リッチ・メディーナは90年代前半から、アフリカ音楽の収集家だった。しかしその頃はこの音楽がなかなか受け入れてもらえなかったと、メディーナは思い出す。「クラブの客をドン引きさせてたね。(自分が)チャカ・カーン、ジョージ・ベンソン、アース・ウィンド&ファイアなんかをかけると盛り上がって、お互いに酒をかけ合ったりしてはしゃいでいた客が、(フェラの)“Shakara” をかけた途端に……まるでゴキブリでいっぱいの部屋で明かりをつけたみたいになった」。
MUTE BEAT
“MUTE BEAT”と聞いてまず思い出したのは、2008年、REBELレゲエ誌Riddim の25周年/300号記念に際して恵比寿リキッドルームにて行われた、約20年ぶりの“一夜限り” の再結成ライブ。とはいえ、そのライブさえも見逃した75年生まれの自分に、80年代を駆け抜け解散してしまった、日本が誇るライブDUBバンドの全貌を知る方法は、残された作品群を聴き、当時を知る方々のお話を読み聞きするしかない。まず、その再結成を仕掛た張本人、OVERHEAT代表、石井“EC”志津男氏を訪ねた。
Don Letts
クリエイティヴ・アートにルネッサンスをもたらした男、ドン・レッツ。ジャマイカ人キャストのみを招き、全撮影をジャマイカで敢行した『Dancehall Queen』の監督として最も良く知られる彼は、自身のヴィジョンを多彩な分野で実現させてきた。ただし、型にはまらない音楽に関わり続ける、という点でその才能は常に一貫している。ドン・レッツは、禁断の恋を描いたキマーニ・マーリー主演の『One Love』を共同監督したほか、ミュージック・ビデオを数百本ほど手掛けてきた。
Guru
あの声。ザラザラして耳につく、聴けばすぐに彼だとわかるあの声。ぶっきらぼうでありながらも情熱を宿したあの声……。本当にたくさんのヒップホップ・ファンにとって、あの声こそがグールーの個性そのものだった。
Teddy Pendergrass
ワックス・ポエティックス・ジャパンNo.09に掲載されたテディー・ペンダーグラスのインタビューのときは対立的な関係になってしまい、「取材した日、彼は機嫌でも悪かったのかい?」と読者によく言われることがあった。
Saravah Soul
現在進行形ファンク・シーンを牽引するUKのTru Thoughtsの中でも、サラヴァ・ソウルは異彩を放つバンドだ。ブラジルの血を引くリーダーのオットーを始め、彼らは多国籍バンドで、それがサウンドにも明らかに表れている。
Jeb Loy Nichols
現在、ジェブ・ロイ・ニコルズはウェールズの片田舎に住んでいる。聞くところによると自宅にはネット環境もないそうで、ちょっとした連絡を取るためには近くの町までわざわざ出向かないといけないらしい。
Incognito
インコグニート。昨年結成30年を迎えたこのバンドを、90年代のアシッド・ジャズ期に生まれたグループだと思っている人は多いのではないか。私もその1人だった。彼らがキャリアの集大成とも言える渾身の新作を完成させた。
Funky DL
ファンキーDLが日本でデビューしたのは、キャリア4作目『When Love Is Breaking Down...』の日本盤が発売された2000年のこと。10年前の話だ。この10 年間に彼は着々と作品を作り続け、リスナーの心を常に満たしてきた。
Soft
まるでヴードゥーの祭儀のようなアフロ・パーカッションの、その呪術的かつ恍惚とした響きから始まるライブ・アルバム。京都を拠点に15年以上も活動を続けるバンド=SOFTの、最近のライブ模様を切り取ったドキュメントだ。
Marcos Valle
いまでも忘れられない。マルコスが私の記憶に焼きついて離れない。1995年、一緒にリオのスタジオで仕事をしたときのことだ。その朝、息子を学校に送った彼はその足でサーフィンをするため海岸に向かう途中だった。
Flowering Inferno
Tru Thoughtsの看板アーティストとして活躍し、ファンクやブレイクビーツに軸足を置いた作品作りを続けてきたクァンティック。彼の作品が世界各地で高く評価されてきたことは、あえてここで強調するまでもないだろう。
12×12: The Breaks
2006年初頭、グランドマスター・フラッシュがスミソニアン国立アメリカ史博物館のヒップホップ常設展示へ寄贈を求められた時、彼はミキサーとカンゴール・ハットと共に、使い込んだ2枚の12インチ・シングルを選んだ。
The Five Corners Quintet
2004年のフィンランドにおいて、クラブ・ジャズという世界から飛び出してきたファイヴ・コーナーズ・クインテットだが、今ではクラブ・ジャズという限定的な枕詞をつけることなく、ジャズ・バンドとして評価されている。
Jay Rodriguez
過去2回、グラミー賞にノミネートされたこともあるジェイ・ロドリゲスはサックス、フルート、クラリネットをはじめ、キーボード、パーカッションを演奏するマルチ・ミュージシャンであり、作曲家、編曲家である。
The 45 Adapters
45アダプター。この発明品よりも便利で上品でシンプルなものはあまりない。たいていの人はアダプターも7インチ盤の中にそのままはめておくので、かなりたくさんこの小さくて薄い円盤状のものがたまっていることになる。
12inch Laboratory
こんにちは! 今回から気分も新たにこのコーナーのデザインも一新され、より読み易くするべく枚数も8枚から6枚と更に厳選してのご紹介。当分の間はテーマ性を持たず、自由気ままに色んな性格の12inchを紹介して行きます。
ヴァイナル駅伝
今号の特集がフェラ・クティとトニー・アレンということで、ワールドカップも含め。今ノリにノッているアフロ・ファンクにスポットを当てて、母なる大地をアベベばりに突っ走ってみたいと思います(もちろん、裸足で)。
Funk Archaeology
1970年代中盤、ザンビア共和国は苦境の時代を迎えていた。同国の初代大統領、ケネス・カウンダと同氏率いる統一民族独立党は、イギリスの植民地支配から既に脱していたが、紛争が内陸国ザンビアの四方を囲っていた。